映画『怪物』というタイトルを見たとき、多くの人が思い浮かべたのは「誰が怪物なのか」という問いだったのではないでしょうか。
物語は、ある出来事をきっかけに、疑いの視線が少しずつ向きを変えていきます。
そして観終えたあとに残るのは、単純な犯人探しではありません。
本当に問われていたのは、「怪物とは何か」という私たち自身への問いだったのかもしれません。
ここから、その核心を整理していきます。
怪物は“誰か一人”ではなかった

物語の中で、怪物のように見える人物は、たびたび入れ替わります。
教師。
親。
子ども。
ある視点では加害に見えた行動も、別の視点から見るとまったく違う意味を持ち始めます。
本作は、特定の誰かを断罪する物語ではありません。
むしろ描かれていたのは、「怪物」という言葉がどれだけ簡単に貼られてしまうのか、その構造そのものだったのではないでしょうか。
視点が変わるたびに、怪物の輪郭も揺らぐ。
そこに、この作品の静かな衝撃があるのです。
社会という構造の中で生まれる怪物

本作が描いていたのは、個人の異常性だけではありません。
噂。
思い込み。
立場の違い。
そうした要素が重なり合うことで、誰かが「怪物」として扱われていきます。
怪物は突然現れるのではなく、関係性の中で少しずつ形づくられていくのかもしれません。
特定の誰かを責めるのではなく、空気や構造そのものを問いかける。
そこに、この作品の社会性が見えてきます。
それでも問いは観客に残された

『怪物』は、明確な答えを示しません。
誰が正しかったのか。
何が間違っていたのか。
その判断を観客に委ねたまま、物語は終わります。
だからこそ、『怪物』は観る人によって印象が変わります。
怪物が誰だったのかを決める物語ではなく、自分はどの視点で見ていたのかを問い返される物語。
そこに、この映画の余韻が残ります。
まとめ

『怪物』が問いかけたのは、特定の人物の善悪ではありませんでした。
怪物は誰か一人ではなかった。
視点が変われば、怪物の姿も変わる。
そしてその背景には、社会という構造が横たわっている。
明確な答えは用意されていません。
だからこそ、『怪物』は観る人によって違う物語になるのです。
なお、本作の「視点が切り替わる構造」については別記事で整理しています(→記事①)。

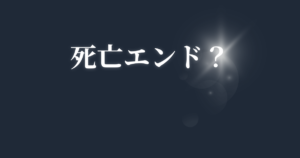


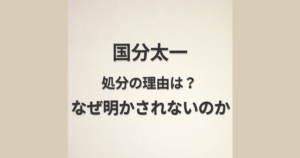



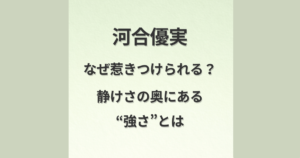
コメント